「ブログをはじめたけど全然読んでもらえない」
「みんなに読んでもらえるブログ記事はどうやって書いたらいいんだろう」
「閲覧数(PV)が増える記事を書くコツってないのかな」
ブログをはじめたのはいいけれど、なかなか成果が出ず上記のような悩みや疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。
私も『読者を集められる記事』いわゆる読んでもらいやすい記事の書き方のコツを掴むまでまでは、同じような悩みを抱えて苦労しました。
読んでもらいやすい記事の書き方のコツは書き方さえ分かってしまえば誰でもすぐに実践できます!
ということで、早速ですが結論から申し上げますと、、、
読者を集められるブログ記事の最大のコツとは「読みやすい記事」を書くことです!!
たったこれだけ?
と思う方もいるかと思いますが、実際これができていない人がすごく多いです。
そこで、今回は実際にコツを掴んで読者を集められるようになった私が、読みやすい記事を書く方法を紹介します!
「読みやすい記事」になぜ読者が集まるのか
そもそも、なんで「読みやすい記事」が読者を集められるのかがわからない方もいるかと思います。
それは『検索エンジン(Googleなど)』と『人の心理』の両方で効果があるからです。
では、実際にどのような効果があるのかをそれぞれ説明していきますね!
検索エンジンでの効果:滞在時間を長くすることができ、検索順位を上げられる
SEOの評価は検索順位と密接に関わっていて、評価が良いと検索順位が上がります。
検索順位が上がると自然と読者の目につきやすくなるため、読者が集まりやすくなります。
SEOの評価で、ブログの滞在時間の長さは重要な指標の1つとなっており、読みやすい記事を書くことで滞在時間を長くすることができます。
そのため、読みやすい記事はSEOに高く評価されやすく、検索順位が上昇するため読者の増加に繋がります。
なんで読みやすい記事は滞在時間が長くなるのか、
それは次に説明する『人の心理での効果』で説明いたします。
人の心理の効果:読むモチベーションを保ったまま最後まで読んでもらえる
読みやすい記事は、最後まで読んでもらえる可能性が高くなります。
逆に、人間は理解に時間がかかったり難しい文章を読むと、読むモチベーションが落ちてしまいます。
実際にあなたが何かを調べたりブログを読んだりする時を想像していただくとわかると思いますが、
いくら有益な情報を扱っていても、難しい専門用語だらけの記事だったり、論文のように文字がやたらと詰まっているような記事は読みにくいですし、読む気になりませんよね。
反対に、簡単に理解できるような読みやすい記事はストレスを感じず、読むモチベーションを保ったまま最後まで読めてしまいます。
このような心理から、読みやすい記事は滞在時間が長くなりやすいのです。
また、読みやすい記事が書いてあるブログは認知されやすく、今後他の記事も読んでもらえる可能性が高くなります。
これらの効果が働くことで、読みやすい記事は読者が集まりやすいのです。
ここまで読んでくださった方は、読みやすい記事を書くことがどれだけ重要なのかは理解していただけたかと思います。
なので、ここからはどうやったら読みやすい記事を書くことができるのか
誰でもできる超簡単な6つのコツをお教えします!
読みやすい記事を書く6つのコツ
ここまで、読みやすい記事はなぜ読者を集められるのかを説明しました。
ここからは、読みやすい記事を書くための6つのコツを紹介します!
- 子供でも理解できるような言葉選びを意識する
- 文章構成を考えてから書き出す
- 語尾の形式を統一する
- 余白や改行・句読点を入れてメリハリをつける
- 強調したいところには色や太字を使う
- 【最重要】時間を少し空けてからもう一度確認
1.子供でも理解できるような言葉選びを意識する
まず1つ目のコツは、子供でも理解できるような言葉を意識して記事を書くことです!
専門的な内容の記事を書く場合でも、なるべく子供でも理解できるような言葉選びを意識することが重要です!
記事を読んでくれる方の大体はわからないことだったり、問題を解決するために調べている方達です。
にもかかわらず、難解な言葉や専門的な言葉でまわりくどい言い回しをしていたりでは内容が理解しにくいため、問題を解決出来ません。
そのため、専門的な部分でもなるべくわかりやすい文章に置き換えるなどして、子供でも理解できるような言葉選びを意識して記事を書きましょう!
2.文章構成を考えてから書き出す
2つ目のコツは、文章の構成を考えてから記事を書きだすことです。
構成も何も考えずに記事を書いてしまっている人、今これを読んでくださっている方の中にもいるのではないでしょうか。
いきなり書き出してしまうと、文章のつながりがおかしくなったり、何を誰に伝えたい記事なのかがわかりにくくなってしまったりします。
そうすると、読者はおろかGoogleなどの検索エンジンの評価も良くないものになってしまいます。
ブログ記事を書く際には、
- どのような問題を抱える人物に対して
- どのような情報を
- どのように伝えるか
がとても重要になってきます。
なので、少なくとも上記のポイントは意識して、記事の構成をしっかり設計してから書き始めるようにしましょう!
3.語尾の形式を統一する
3つ目のコツは、記事中の語尾の形式を統一することです!
これは、「です・ます」調と「だ・である」調などの異なる文調を混ぜて使用しないことです。
記事の最初は「です・ます」で文が終わっているのに、途中から急に「だ・である」で終わるようになってしまっていたら違和感を感じますよね。
このような違和感は読者側からしたらストレスに感じるため、読むモチベーションが落ちてしまい記事を最後まで読むことなく離脱してしまいます。
そのため、ストレスなく最後まで読んでもらえるよう語尾の形式は統一しましょう!
4.余白や改行・句読点を入れてメリハリをつける
4つ目のコツは、文章に余白や改行・句読点を入れてメリハリをつけることです!
文章がぎっしり詰まっていたり改行が全然ないような文章は、読むのに疲れてしまいます。
実例として、下の例文をご覧ください。
(実例)
このような感じで文章に改行がなかったり余白や句読点が全くないと最後まで気を張り詰めて読む必要があります。その結果読者は気を抜くポイントがわからず読んでいるだで疲れてしまいます。また文章中から重要な部分を探しだすことが困難となり気楽に読みに来た読者は読む前から離脱してしまいます。そうすると滞在時間はおのずと短くなってしまうため検索エンジン側の評価も下がってしまい読者が増えづらくなります。
上記の実例のような文章、すごく読みにくいですよね。
そもそも、できれば読みたくないのが本音だと思います。
余白や改行・句読点がない文章は読むことがストレスに感じてしまい、読者の離脱につながります。
なので、文章の適切な部分で改行や余白・句読点を入れて読みやすくすることが重要です!
5.強調したいところには色や太字を使う
5つ目のコツは、強調したいところには色や太字を使用することです。
色や太字は視覚的に目立つため、読者は重要な部分だと認識することができます。
記事に訪れる読者の中には、「重要な部分だけささっと知れればいいや」と流し読みで記事を読む人も大勢います。
結論などの文章中の大事なところに色や太字を用いることで、どのような読者も読み落とすということがなくなるため、記事の内容を把握してもらいやすくなります。
ただし、むやみやたらに色を付けたり、太字にしたりすると本当に重要な部分がわかりにくくなってしまうため注意しましょう。
6.【最重要】時間を少し空けてからもう一度確認
最後、6つ目のコツは、記事が書き終わったら少し時間を空けてからもう一度確認することです。
これが「読みやすい記事」を作るには非常に重要な部分になります!
記事を書き終えてすぐは達成感や集中していたための疲れなどが影響して誤字脱字や文章のおかしな表現などに気づくことができない場合があります。
最低でも30分は時間を空け、もう一度確認してみましょう。
今まで気づけなかった誤字脱字などの間違いを見つけることができ、投降後の記事がより完成度の高いものになります!
また、記事を書き終えてすぐの状態は、記事を書く上で仕入れた情報などが頭の中に鮮明に残っているため、記事を書いている時は「わかるだろう」と思っていたことも、後々になって確認してみると「やっぱり伝わりづらいな」ということもあります。
なので、誤字脱字などの確認だけでなく、内容が理解しやすい記事であるかを判断するためにも記事を書き終えてもすぐに投稿はせず、時間を空けて再度確認してみることが重要です!
まとめ:読みやすい記事を継続して書くことが大事
今回は、読者を集められる記事である『読みやすい記事』の書き方のコツを紹介しました。
いざ「読みやすい記事」が書けるようになって、早速記事を投稿してみても、はじめのうちはなかなか読んでもらえない状態が続くかもしれません。
しかし、そこで諦めてしまうようなことは絶対しないでほしいです。
なぜかというと、それは検索エンジンのSEO評価の効果があらわれるまでに時間がかかるためです。
良い記事であれば時間がかかったとしてもほぼ確実に評価してもらえます。
評価してもらえるまで「読みやすい記事」を書き続けることで、その後の閲覧数は格段に増えていきます。
ブログは諦めずに続けられる人が報われやすいです。
なので、今回の「読みやすい記事」の書き方のコツを参考に、ブログ記事の更新を続けていただけたら幸いです!
以上となります。
最後までお読みいただきありがとうございました。


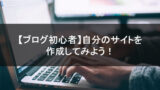


コメント